こんにちは ツナカンです。
私はふだん
適応指導教室のカウンセラー(公認心理師)として
不登校のお子さんや
子育てに悩む保護者の方
学校の先生方
の相談にのっています
お子さんが不登校になると
親御さんはとても心配し
何とかして学校に行かせようとします。
しかし,お子さんはなかなか行こうとはしません。
また,その理由もわからず

どうやったら学校に行けるようになるの?
と頭を抱えてしまいます。
こうした相談は毎年何件もあります。
しかし,お子さんの状況も
家庭の状況もさまざまですので
どうやったら学校に行けるようになるのか
あるいは
学校に行かせること自体が正解なのか
なかなか答えは出せないものです。
そこで今回は
お子さんに「学校に行こう」と言って良いタイミング
についてご紹介します。
この記事を読んでもらえれば
こんなことがわかります。
- 学校に誘ってもよい時の兆候5つ
- 声のかけ方,抑えるポイント4つ
- 登校刺激
- どのくらいの子が学校に戻れるのか
これを読んでいただければ
お子さんがまた学校に行けるようになる
タイミングを見つけやすくなります。
また家族関係が悪くなってしまいがちな
不登校問題の解決のヒントになると思います。
なお,この記事では学校から遠のいてしまっていて
改めて学校と向き合おうとする段階のお子さん
を想定しています。
学校に誘っても良い兆候5つ

学校に行けないお子さんに
無理に行かせても,多くの場合良いことはありません。
一時,回復したように見えても
また行けなくなることが多いからです。
行けていない時間を注意深く観察し
学校に誘うタイミングを見計らう必要があります。
そのポイントは以下の通りです。
- 家庭以外に安心できる場がある
- 家族に悩みを打ち明けている
- 将来の夢を持っている
- 学校の情報がある程度わかっている
- 生活のリズムが整っている
その①:家庭以外に安心できる場がある
学校に行けなくなった時
保護者はその理由を知りたいと思うのは当然です。
しかし,子どもの方は

家族だからこそ言えない
そんな気持ちであることを何度も聞きました。
親を心配させたくない
親に怒られるんじゃないか
どうせ話してもわかってもらえない
親の気持ちはわかるけど,自分でもなんて言ったらいいのかわからない
お子さんたちはそんな風に言います。
ですから,家庭だけで抱え込まずに
お子さんにとって安心できる場を
用意してあげるのも方法の一つです。
それが適応指導教室やフリースクール
あるいは,親せきの家とか
友だちの親だということだってあります。
とにかくお子さんにとって居心地の良い場所がある
ということが大切でしょう。

その②:家族に悩みを打ち明けている
家族に悩みを打ち明けるということは
お子さんの気持ちを理解するチャンスです。
そこから具体的な対処法を考えることもできます。
一方,家族に打ち明けていないなら
家族に対する警戒心を持っているということです。
注意しておきたいのは

とにかく,学校に行きたくない!
というような表現の時です。
これは打ち明けているのではなく
意思の表明です。
まずは,その意思を受け止めましょう。
そして,理由を聞いても答えられないなら
無理に聞くことはせず
まずは現実的にどの程度学校にコミットするのか
話し合いましょう。

その③:将来の夢を持っている
将来の夢は困難と向き合うための重要な武器です。
夢があれば,学校に行く必要性がわかっているので
学校に誘われても大きな不満を持つことはありません。
ただし,

夢があったけどあきらめなきゃいけない
お子さんがそんな気持ちになっている時に

夢のためにも頑張ろう
なんて声掛けは,お子さんの気持ちとはずれがあります。
下手をしたら,

親の方が安心したいからそういうんだ
と受け取られてしまいますから
お子さんのやる気を高めることにはなりません。
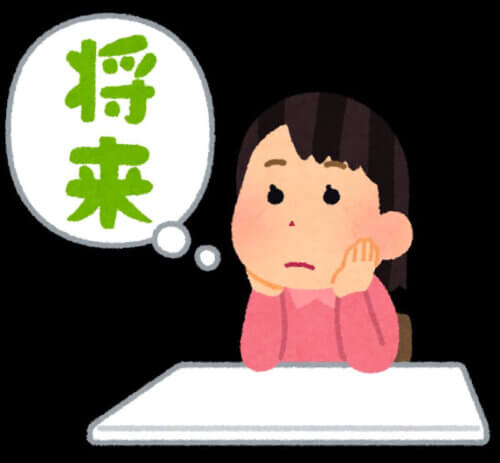
自分の夢のためにもやってみたいんだけど…
そんなニュアンスの時に背中を押してあげる
そんなタイミングが良いでしょう。

その④:学校の情報がある程度わかっている

誰でも同じだと思いますが
これから向かうところの情報は
前もって知っておきたいものです。
お子さんからすれば学校の復帰は大冒険です。

前に行ってたんだから大丈夫
なんて言いがちですが
学校は常に変化していますから
できるだけ新鮮な情報を
知っている時には安心感も高まります。
その⑤:生活のリズムが整っている

生活のリズムが整っていると
色々なことに挑戦してみたくなるものです。
また,生活のリズムの立て直しをしようとしているということは
何らかの目的があるからです。
学校以外の目的で立て直そうとしているのかもしれませんが
少なくとも前向きな行動ですから
さりげなく,学校のことを話題にだしてみて
様子をうかがっても良いでしょう。
声のかけ方抑えるポイント4つ
お子さんを学校に誘う時に
抑えておくと良いポイントがあります。
- あくまでも提案
- 話し合える状態・環境であること
- 今よりほんのちょっとだけ進めば良いし失敗しても良い
- 子ども自身の感覚に焦点を当てる
その①:あくまでも提案

普通は

学校は行くべきもの
と思ってしまうものですが
不登校ではこんな常識は崩れています。
それは良いとか悪いとかではありません。
常識が全くないのであれば
教えれば良いのです。
しかし,常識がないのではなく,崩れているのです。
だから,提案なのです。

提案しても「嫌だ」と言われたらどうするの?
そうなのです,実際に私も嫌だと言われたこともあります。
でも,嫌だと言える関係性が大事なのです。
その②:話し合える状態・環境であること

どんな会話でもそうなのですが
お互いが話し合える状態だったり
話しやすい環境でなければ通じ合うことはできません。
まず,お子さんの状態を確認してから声をかけましょう。
また,その時に邪魔になるものがあるなら取り除きましょう。
そのためにも前もって,時間と場所を約束しておくと
お子さんも心の準備をしやすくなります。
その③:今よりほんのちょっとだけ進めば良いし失敗しても良い
学校に行けなくなったお子さんは
大きな挫折感を持っていることが少なくありません。
いくら少し前向きになったとしても
失敗は重ねたくないはずです。
ですから,成功体験を積み重ねていくことが大切です。
最初に
今より,ほんのちょっとだけうまくいきそうなことをしてみる
失敗をしても良い
そんな保証をしておくと良いでしょう。

その④:子ども自身の感覚に焦点を当てる
先にも学校に行けなくなったお子さんにとって
「学校は行くべきもの」という常識は
崩れた状態であることをお伝えしました。
ですから,あくまでも
お子さんにとっての価値感に合わせて
- 学校がどんな役に立つのか
- 学校に行くことのデメリット
を伝える必要があります。
それらを一緒に考えてみて
学校に行くことの方がメリットが大きいとなれば
お子さんは,さらに学校に行く勇気を奮い立たせてくれるでしょう。

登校刺激
ここまで学校に誘うタイミングやポイントをご紹介してきました。
学校に誘うことを
登校刺激
と呼びます。
登校刺激の良し悪しについて以下のようなことが言われています。
登校刺激の良し悪しは『子どもの反応』によって左右される
- 登校刺激の是非の判断は,まず子どもの反応次第である。刺激と評価は一対である
- 発達段階によっても対応は異なる。自動機では適切な登校刺激が功を奏しやすい
- 不登校の経過の後期では,なんらかの後押し(登校刺激)が必要となる
山本力(2005)不登校の子ども支援に関するガイドライン試案.岡山大学教育実践総合センター紀要,第5巻.pp.131-137.
数十年前までは
積極的に登校刺激を与える時代がありました。
しかし,それが良くないことがわかってくると
登校刺激は悪いものだ
と言わんばかりに登校刺激に消極的になりました。
しかし,登校刺激は必ずしも悪いものではなく
登校刺激の良し悪しは子どもの状態による
ということが言われているのです。

どのくらいの子が学校に戻れるのか
文部科学省からは不登校になっても
学年とともに学校復帰率は上がる というデータが出ています。
小学校では42%,中学校で35%,高校で43%
が戻っているとされています。
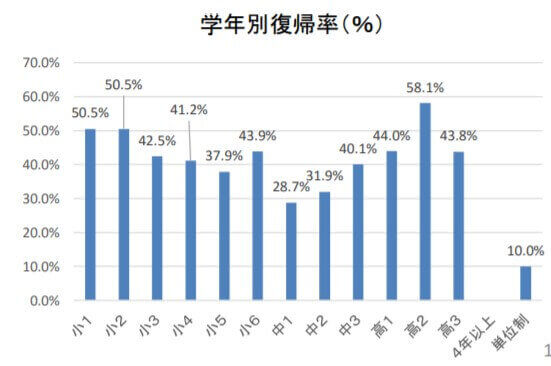
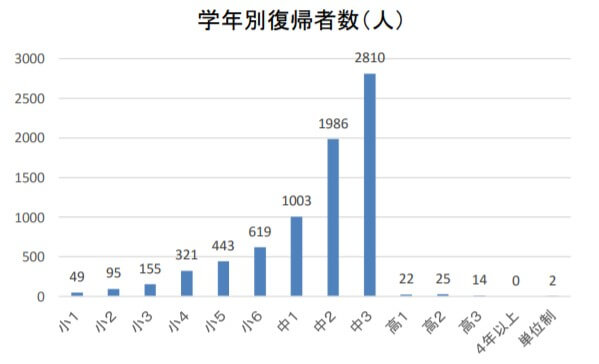
引用:文科省(2019)教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果
表を見ると復帰率の数字に反して
中学校3年生で急に伸びているように見えるのは
- 高校入試を見すえて学校に復帰
- 小学校からの長期不登校生徒が学校に通い始める
ということだろうと見ています。
そう考えると,楽観はできないまでも
自分なりに将来を考えているお子さんは多いと言えるでしょう。
また,高校生で不登校の数が少ないのは
高校での不登校は退学に直結するからでしょう。
このように,例え学校に行けなくなったとしても
遅かれ早かれ多くのお子さんが
また学校に行けるようになっているようです。
もちろん,学校以外の選択肢もありますので
例え不登校になったとしても
お子さんの将来を諦める必要はなさそうです。

まとめ
以上,学校に行けなくなったお子さんの
学校への誘い方についてご紹介しました。
学校に誘っても良いタイミング・状態
そして,誘うときのポイントを抑えて
お子さんに沿うように誘えると良いですね。
また長期化することもあるかもしれませんが
それでも多くのお子さんは学校に復帰していますし
これからの時代,学校以外の選択肢も広がるでしょう。
この記事が,学校に行けないお子さんの親御さんや
お子さん自身のお役に立てることを祈っています。
質問・感想やご相談は以下のリンクまで
お気軽におよせ下さい。
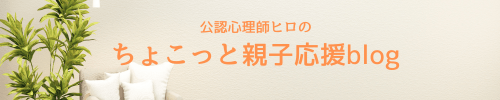



Comments