こんにちは ヒロです。
ふだんは公認心理師として
子育て中の親御さん
学校の先生などのお手伝いをしています。
お子さんが朝起きられず、学校に行けない…。
「なんでだろう?」と原因を探しても、子ども本人も「分からない」と首をかしげる。
友人関係、勉強、家族の問題…色々な要因が挙げられるけれど、
これといった決め手が見つからず、
途方に暮れている保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は今、
不登校の背景に「生活リズムの乱れ」や「睡眠の問題」が深く関わっている
ことに、大きな注目が集まっています。
今回は不登校と睡眠リズムについてお伝えします。
これを読んでいただくと
お子さんの不登校の理由や
不登校になったお子さんに対して注意すべき点について
知ることができます。
不登校の「本当の理由」はどこに?意外な調査結果

これまで、不登校の原因は人間関係や学習面にあると思われがちでした。
もちろんそれらも複雑に絡み合っています。
しかし、最近の調査では、意外な「本音」が見えてきています。
- 「無気力、不安」と並んで、小中学生の不登校の理由として挙げられるのが「生活リズムの乱れ、遊び、非行」。特に小学生では13.1%、中学生では11.0%にものぼります(令和3年度 文部科学省調査)。
- 日本財団の調査では、「学校に行きたくない理由」の1位が「疲れる」、2位が「朝、起きられない」という結果に!年間30日以上欠席する中学生では、なんと半数以上が「朝、起きられない」と答えています。
- さらに、不登校の子どもたちの医学的な問題を探る研究では、60%に「睡眠障害」が、57%に「神経発達症」が見られたという報告もあります。海外の大規模研究でも、「睡眠・覚醒相後退障害は不登校のリスクである」と指摘されているんです。
これらのデータから、お子さんの「朝起きられない」という状態が
単なる怠けではなく、医学的な睡眠の問題と密接に関わっている可能性
が見えてきます。

もしかして「睡眠・覚醒相後退障害」? 朝起きられない子どもの診断名
「朝起きられない」と訴えるお子さんで不登校に陥っている場合、
専門家は以下のような診断名を検討することがあります。
- 睡眠・覚醒相後退障害:体内時計が一般的な時間帯よりも大幅に後ろにずれてしまう状態。夜中に眠れず、朝起きられない典型的なパターンです。
- 不規則睡眠・覚醒リズム障害:毎日寝る時間も起きる時間もバラバラで、決まったリズムがない状態。
- 非24時間睡眠・覚醒リズム障害:体内時計の周期が24時間からずれてしまい、日によって寝起きのリズムが大きく変わる状態。
これらは総称して

「概日リズム睡眠・覚醒障害」
と呼ばれ、不登校の原因となることもしばしばです。
加えて、
日中の強い眠気や、
11時間以上続く過度な長時間睡眠(過眠症)
が見られることもあります。

そして、これらの睡眠の問題に
神経発達症が合併しているケースも少なくありません。
特に小学校高学年から中学2~3年生にかけて
こうした状態が見られることが増えると言われています。
家族の生活習慣が不登校を招く?見過ごされがちなサイン
お子さんの不登校と睡眠の問題は
実は家族全体の生活習慣と密接に関わっていることがあります。

- 家族全体が夜型の生活を送っている。
- お子さんが自分用のスマートフォンを購入したり、ゲームに没頭したりするのをきっかけに、就寝時刻がずるずると遅くなってしまった。
- 部活動や塾などの課外活動が忙しく、睡眠時間が確保できていない。
- 遠方の学校に進学したことで通学時間が長くなり、睡眠時間が短縮されている。
- 朝の起床が困難なのに、家族の協力でなんとか起きている状態が続いている。
- 学校で居眠りをしているなど、睡眠不足のサインが見られても、本人や家族、先生が「周りの子も似たようなもの」と考えてしまい、問題の改善に着手しない。結果、極端な成績低下や不登校になって初めて異変に気づく。
また、友人関係のトラブルや学習の困難感などがきっかけで
ストレスから睡眠・覚醒相後退障害に陥るケースもあります。

中には、起床困難を訴えて小児科を受診し
「起立性調節障害」と診断されて治療を受けるものの
一向に改善しないというケースもあります。
このような場合、背景に睡眠障害が隠れている可能性も視野に入れる必要があります。
睡眠の問題は「ニワトリとタマゴ」?不登校を長引かせる要因
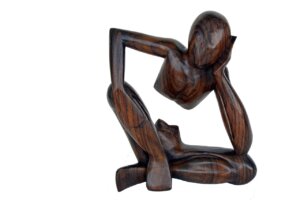
「睡眠の問題のせいで不登校になるのか、それとも不登校になったから睡眠に問題が生じるのか?」
これはまさに

「ニワトリとタマゴ」の関係で、
どちらが先かはケースバイケースです。
しかし、はっきり言えるのは…

睡眠の問題が不登校を長引かせる大きな要因の一つとなる
ということです。
解決のヒントは「体内時計」のズレにあり!社会的ジェットラグとは?
では、なぜ現代の子どもたちはこんなにも睡眠問題を抱えやすいのでしょうか?
その鍵となるのが…
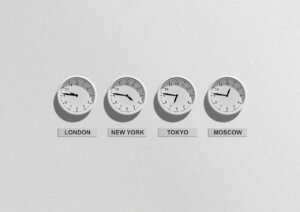
「社会的ジェットラグ」
です。
健康な子どもの推奨睡眠時間は、米国睡眠医学会によると、
- 6~12歳で9~12時間
- 13~18歳で8~10時間とされています。
しかし、日本の小中学生の平均睡眠時間は
小学生で約8時間台、中学生では7時間台と
多くの児童生徒が推奨時間を確保できていません。

この睡眠不足の背景には、思春期に起こる
「夜型化」という生物学的な変化があります。
夜間のメラトニン分泌のタイミングが遅れ
体が眠気を感じるまでの時間が長くなることで
生理的に睡眠相が最大で約2時間も後退し、夜型になるのです。

さらに、スマートフォンやゲームなどの夜間のメディア使用、
通学や部活動、学習といった社会的な影響が加わり
夜更かしが助長されます。
平日は遅刻しないよう早朝に起きる必要があり
このギャップが睡眠時間を減少させ、睡眠負債を積み重ねていきます。

そして、この睡眠負債を解消しようと、休日に遅くまで寝ることで
平日と休日の睡眠時間帯がずれてしまいます。
これがまさに「社会的ジェットラグ」!
体内時計が混乱し、様々な心身の不調を引き起こす原因となるのです。

実際、文部科学省の調査(平成26年度)では、
小学生の42.5%、中学生の57.0%が
「平日と休日で起床時刻が2時間以上ずれることがある」
と回答しており、多くの子どもがすでに
社会的ジェットラグ の状態にある可能性が示唆されています。

慢性的な睡眠不足と社会的ジェットラグが続くと
感染症などをきっかけに一気に起床困難になり
不登校に陥るパターンも少なくないのが現状です。
まずは「生活リズム」を見直そう!親ができること
お子さんの不登校の背景に睡眠の問題があると感じたら
まずは日々の生活リズムを見直すことから始めてみましょう。
特に、夜間のスマートフォンやゲームの使用は
睡眠の質を大きく低下させ、体内時計を乱す原因となります。

しかし、一度手にしたものを子どもから取り上げるのは至難の業ですよね。
そこで有効なのが、ゲームやスマートフォンの「時間管理」です。

ゲームやスマホとの付き合い方、悩んでいませんか?
「もう夜だからやめなさい!」「あと少しだけ…」毎晩繰り返される親子の攻防。
お子さんとの信頼関係を壊さずに、メディアの使用時間をコントロールしたい。
そんな時に役立つのが、デジタルデバイスを安全に保管し
決まった時間までロックできる「時限式の箱」です。
これを使えば、
- 「時間になったら箱に入れる」というルールが明確になり、親子間の無用な口論が減ります。
- お子さん自身も「この時間になったら終わり」という自覚が芽生え、自律的な時間管理を学ぶきっかけになります。
- 親御さんも「取り上げなきゃ」というストレスから解放され、安心して過ごせるようになります。
夜遅くまでだらだらと使い続けることで
いつの間にか睡眠時間が削られていく…

そんな悪循環を断ち切るために、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
お子さんの不登校は、親御さんにとっても本当に辛く、
出口の見えないトンネルのように感じるかもしれません。
しかし、その背景にある「睡眠」や「生活リズム」の問題に目を向けることで
解決への新たな光が見えてくることがあります。

焦らず、お子さんのペースに合わせて、少しずつ生活習慣を整えていくこと。
そして、必要であれば専門家の力を借りることも視野に入れながら、
一緒に歩んでいきましょう。
当ブログでは、これからも不登校の子どもたちと、そのご家族を支えるための情報をお届けしていきます。
オンラインカウンセリングも承ります。

参考文献:平田(2023)子どものこころと脳の発達 Vol.14 No.1
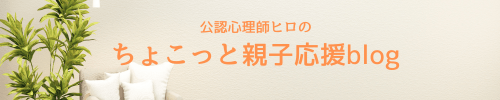



Comments