こんにちは 公認心理師のヒロです。
ふだんは子育て支援機関や教育支援センターで
子育て中の親ごさんの相談や
不登校のお子さんや
学校の先生などを応援しています。
「うちの子があまりしゃべりません」
「家では喋れるのに学校では喋らないと言われます」
世の中には、そんな子が一定数いて、親御さんが悩まれています。
もしかすると、場面緘黙症 と呼ばれる症状かもしれません。
しかし、そんなお子さんでも適切に対処することで
話せるようになりますし、私もそうしたお子さんと
何度か接してきました。
この記事を読むことで、以下のメリットが得られます。
- 場面緘黙症が内気ではなく、そのメカニズムを知ることができます。
- 「話せない」の背景にある理由について、専門的な知見をわかりやすく学べます。
- 効果のある支援方法(段階的エクスポージャー法、注意訓練法など)について、具体的なステップを知ることができます。
- お子さんの特性に合わせた、無理のない、そして希望につながる具体的なアプローチを見つけられます。
その「話せない」は、単なる内気じゃないかもしれない

「うちの子、どうして学校だと話せないんだろう…」

「挨拶もできなくて、失礼だと思われているんじゃないか…」
そう悩んでいませんか?
それはもしかしたら、場面緘黙症 かもしれません。

場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)
は、特定の場所や状況(例えば、学校や習い事)で
話すことが難しくなる状態です。
家では普通に話せるのに、外では全く声が出せなくなってしまう。
これは決して「話したくない」という本人の意思ではなく

「話そうとしても声が出ない」
という、コントロールできない強い不安や緊張が原因なのです。
単なる「人見知り」や「恥ずかしがり屋」とはちがうんです。
「話そうとすると喉が圧迫される感じ」
そんなお子さんは、話そうとすると
体がこわばり
心臓がドキドキする
といった身体的な反応を伴うことも珍しくありません。
これは、話すことへの強い不安が
身体的な発話困難を引き起こすという
心理と身体が結びついた反応だからです。
この状態を理解しないまま

「話す練習をさせなきゃ!」
と無理に促すことは、かえって逆効果になることがあります。
また、場面緘黙症を持つ子どもは
もともと繊細な気質を持っていることが多く
自閉スペクトラム症(ASD) や
注意欠陥・多動性障害(ADHD) といった
発達特性を併せ持つ場合も少なくありません。
一人ひとりの特性を理解し、
その子に合ったきめ細かなアプローチを考えることが大切です。
2. 不安が「声」を消す:ワーキングメモリーとの関係
「話す」という行為は、実はとても複雑な認知プロセスです。
相手の話を聞く → その内容を一時的に覚える → 適切な返事を考える
この一連の流れを担うのが
ワーキングメモリー(作業記憶)
という脳の機能です。
しかし、このワーキングメモリーは
強い不安やストレスに非常に弱いという特徴があります。

「場面緘黙症の子どもは、ワーキングメモリーが弱いから話せないの?」
いいえ、そうではありません。
専門的な研究では、
場面緘黙症とワーキングメモリーには関連がある ことが示唆されていますが
その因果関係は 「不安」が鍵を握っている と考えられています。

極度の不安が脳に強い負荷をかけると
ワーキングメモリーの機能が一時的に低下してしまいます。
その結果、本来持っている言語能力が発揮できなくなり
「話せない」という状態に陥ってしまうのです。

これは、不安という根本原因にアプローチすることが
いかに重要かを示しています。
3. 希望への一歩:段階的エクスポージャー法とATT
では、具体的にどうすればいいのでしょうか?
今、もっとも効果的だとされているのが

「段階的エクスポージャー法(段階的曝露法)」
です。
これは、不安や恐怖を感じる状況に
小さなステップで少しずつ慣れていく訓練です。
このアプローチは

「話しても大丈夫だった!」
という新しい成功体験を積み重ねることなんです。
スモールステップの原則

- 人・場所・活動のどれか一つを変える: 「家で家族と話せる」という状態から始めるなら、練習相手に信頼できる親戚を一人だけ加えたり、誰もいない放課後の教室で少しだけ話してみる。
- 「話す」以外のコミュニケーションから始める: 最初は指差しやジェスチャーから始め、二択の質問、しりとり、音読など、徐々に発話の難易度を上げる。
- 達成感を可視化する: シールやスタンプなどを活用して、小さな成功を積み重ねたことを親子で共有する。
褒め方にも工夫を
ここで気をつけたいのが、褒め方です。
「話せて偉いね!」と過度に褒めると
子どもはかえってプレッシャーを感じることがあります。
表面的な結果を褒めるのではなく

「勇気を出して一歩踏み出せたね」

「練習を続けてすごいね」
といった、本人の内面的な努力や過程に注目して伝えてみましょう。
補助ツールとしての「注意訓練法(ATT)」
「注意訓練法」は、不安の原因となる
「自己注目」(「どう思われるだろう」「失敗したらどうしよう」といった自意識)
を軽減するトレーニングです。

「ワーキングメモリーが弱い子に注意訓練は意味ないんじゃない?」
という疑問を持たれるかもしれません。
しかし、そうではありません。
注意訓練法は、ワーキングメモリーを直接的に鍛えるわけではありませんが、
その機能を妨げている根本原因の「不安」を和らげる効果があります。

不安が軽減されれば
ワーキングメモリーのパフォーマンスも本来の力を発揮できるようになるため
間接的に非常に有効なアプローチとなります。
つまり、段階的エクスポージャー法という「主軸」を
注意訓練法という「補助ツール」でサポートする、という考え方が重要です。

4. 専門家・家族・学校が協力する三位一体の支援
場面緘黙症は「専門家だけで治せる症状」ではありません。
家族、学校、そして専門家が三位一体となって協力することが不可欠です。
- 家庭: お子さんのペースを尊重し、筆談やジェスチャーなど、無理に話させない環境を整える。
- 学校: 教員やクラスメイトが場面緘黙症について正しく理解し、非言語的なコミュニケーションを尊重する配慮をする。
- 専門家: 家族への心理教育や、学校との連携をきめ細かくサポートする。
この三者の連携は、最も重要でありながら、最も困難な部分でもあります。
お父さんやお母さん自身が不安や戸惑いを抱えてしまうこともありますし、
学校の先生が知識を十分に持っていない場合もあります。
そんな時は、書面での情報共有や専門家からの働きかけが
連携を円滑に進める上で効果的です。
焦らず、お子さんの小さな一歩を共に喜び
成功体験をつみ重ねることが、何よりも大切です。
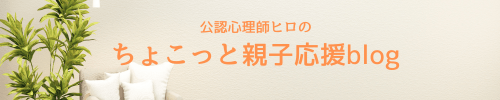
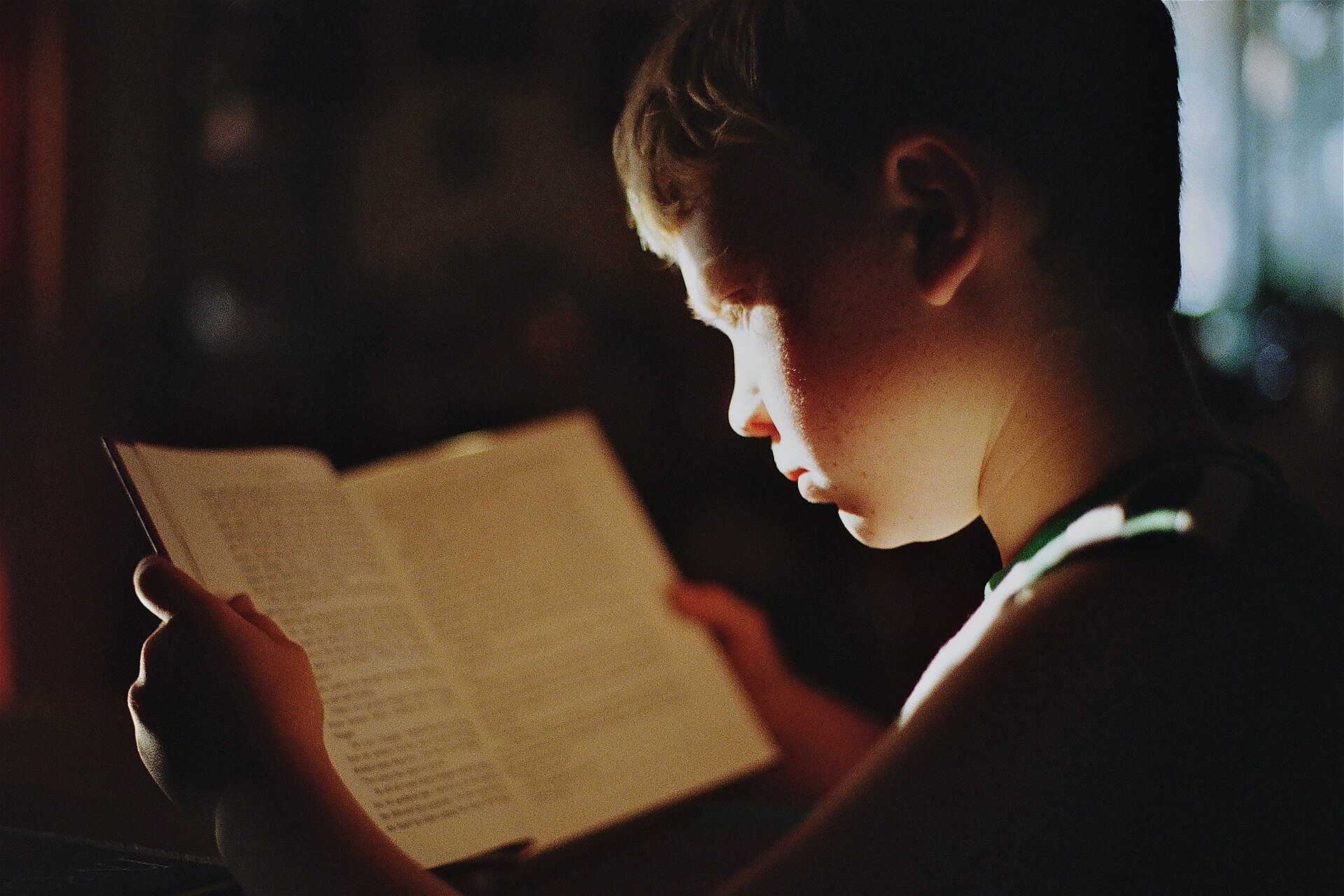


Comments